子ども運動教育学科卒業生たちの学びの先
STATUS OF CAREER
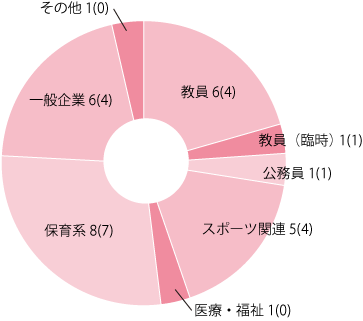
| イベントディレクター 三恵商事株式会社 勤務 |
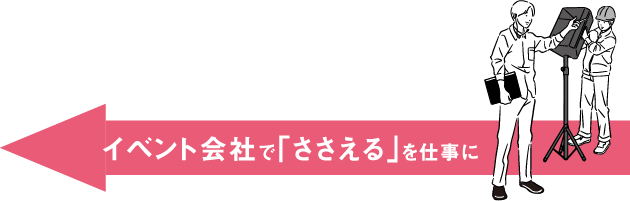 |
|
 |
||
| 大泉 朋希 さん 子ども運動教育学科 卒業 山形県立上山明新館高等学校 出身 Q.今はどんなお仕事をしていますか?
Q.今の場所で自分のどんな力を発揮していますか?
Q.なぜ、今の道を選びましたか?
|
||
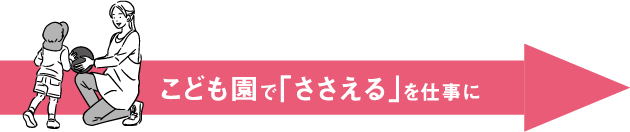 |
保育士 なとり第二こども園 勤務 |
 |
|
| 鈴木 優羽さん 子ども運動教育学科 卒業 福島県立田村高等学校 出身 Q.今はどんなお仕事をしていますか?
Q.今の場所で自分のどんな力を発揮していますか?
Q.なぜ、今の道を選びましたか?
|
| イベントディレクター 三恵商事株式会社 勤務 |
 |
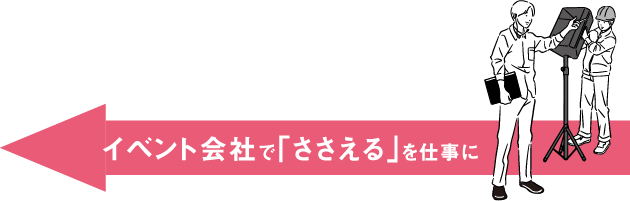 |
|
大泉 朋希 さん
子ども運動教育学科 卒業 山形県立上山明新館高等学校 出身 Q.今はどんなお仕事をしていますか?
Q.今の場所で自分のどんな力を発揮していますか?
Q.なぜ、今の道を選びましたか?
|
| 保育士 なとり第二こども園 勤務 |
 |
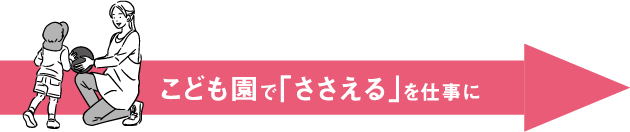 |
|
鈴木 優羽さん
子ども運動教育学科 卒業 福島県立田村高等学校 出身 Q.今はどんなお仕事をしていますか?
Q.今の場所で自分のどんな力を発揮していますか?
Q.なぜ、今の道を選びましたか?
|
STATUS OF CAREER
子ども運動教育学科 卒業生の進路状況
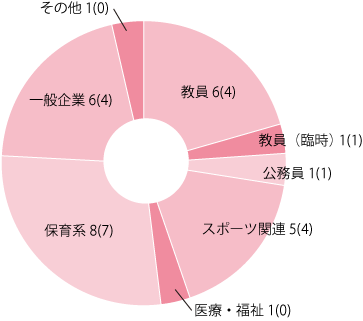
就職率 96.7%
就職希望者数:30名
内定者合計:29名[男子:8名/女子:21名]
※2023年度(令和6年3月卒)
※グラフ内の()は女子内数[2024年5月1日現在]
主な就職先
幼稚園教諭・保育教諭
(学)荒巻学園 あらまき幼稚園、(学)同朋学園 同朋幼稚園、(学)七郷学園 蒲町こども園、(株)ちゃいるどらんど 岩切こども園、(株)ちゃいるどらんど なないろの里こども園
公務員
女川町役場(保育士)、【保育系】、(福)仙台はげみの会 たんぽぽホーム、(福)まあれ愛恵会 川口青木おおぞら保育園、(福)彩福祉会 うぃず千住大橋駅前保育園、AIAI Child Cara(株) AIAI NURSERY 印西牧の原 、(株)キッズフォレ、幼児活動研究会(株)、いいもり山学園
スポーツ関連
(株)デンソー、(株)こども体育研究所、(株)ゴルフレンジ&24フィットネスアミーゴ
民間企業等
宮城トヨタグループ、(株)コジマ、大潟村あきたこまち生産者協会